『光年のかなたデヴォ』
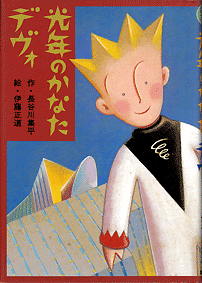
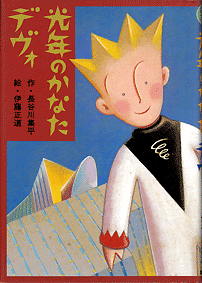
未来の街デヴォに住む12歳の音楽家シラは、「何かを思い出さなければいけない」という考えにとりつかれ、タイム・マシンで20世紀後半の日本へでかける。そこで出会った少女の話から、自分と同じ悩みを持った男の事を知り、時間旅行の謎や、子どもの音楽を流行らせた音楽協会への疑問は強くなっていく。
――思い出せ、思い出せ、思い出せ。ぼくらは何か、大事なことを忘れるように仕向けられてはいないか? この危機感は、他人事じゃないかも……。作者が初めて挑んだSF問題作。
『光年のかなた』の冒頭を少しだけ読んでみてください。
シラは歩いていた。
シラはイナカミチを歩いていた。イナカミチといっても、デヴォにはそんな場所があるはずがない。シラが空間合成機を使って今さっき作ったうそのイナカミチだ。シラがいくつかのボタンをセットし、スタートさせると、がらんどうのデヴォ第2体育館の白いセラミックの地下室が、前にテレビで見たことのある風景に変わった。
私はシラの後ろをついていった。三方を低いなだらかな山に囲まれ、川沿いにくねくね曲がった細いでこぼこ道を、私たちは歩いていた。
「あれ何? おじさん」
シラは向こう岸の黄色い広がりを指差す。
「イネだろう。タンボなんだ。これはアキなんだよ、きっと。そろそろ収穫の季節だ」
「イネ? あ、そうか、わかったよ。食料のイネね」
「うん、こんなものを食べてたんだねえ、昔の人は」
シラは歩き続けた。私はシラと並んだ。「しかし、どうして君はこんなところを歩こうと思ったんだい? またシラ大先生の突飛な思いつきが始まったのかな」
「音楽家はイナカミチも歩く必要があるんだよ、おじさん」
「ははあ、ベートーヴェンに習おうとしているな。彼はたしか散歩が好きで、イナカミチの印象を『田園』という交響曲に書いているからね」
「さすが博学だね、おじさん。でもぼくは、そんなふうにスケッチするやり方で音楽を書きたいんじゃないよ。リズムのことを考えてるんだ。ほら、こうやって原始的な道を歩いていると、いちッにッいちッにッ、ね、歩き慣れたデヴォの道と違うよね。歩いてみるとよくわかるんだ。いやになっちゃうぐらい歩きにくい。このリズムを身体で確かめたいんだ」
「私にはただのでこぼこ道にすぎないけれど、君にとってはアイデアの宝庫なわけだ」
シラは去年でビューした音楽家だ。再来月に12歳になるはずだ。……
●もとは二十代で書いた「デヴォのシラ」という子ども向け連載SF小説。デヴォはそのころ大好きだったバンド、ディーヴォ(DEVO)からつけた地名。未来都市デヴォで苦悩する少年音楽家シラの物語。「思い出せ」がキーワード。──集平Twitterより 2022年6月1日