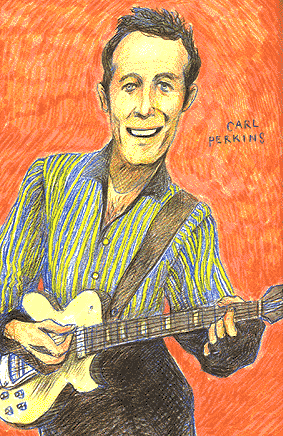「ぼくが死ぬようなことがあったら、ここでぼくが言っていることをきっと思い出してほしい。命の輝きに満ちている愛の言葉なら、決して捨て去られてしまうようなことはないのだ」(アーロ・ガスリー)
たぶん日本のシンガー・ソングライターが学び損なった重要な問題がある。アーロ・ガスリーを聞き直して、間違いないと思った。
ぼくらはPPMやブラザース・フォーで60年代アメリカのモダン・フォーク運動にあこがれを持ち、ジョーン・バエズに声を合わせた。やがてピート・シーガーや、ニュー・ロストシティ・ランブラーズがそのルーツを明らかにしていく手腕に驚いた。ボブ・ディランが出現し、それから彼らの精神的な父親、ウディ・ガスリーのことを知った。そのころ活躍していたディランやトム・パクストン、フィル・オクス、ジャック・エリオットたちは、「ウディの子どもたち」と呼ばれた。彼らを学ぶことからぼくらのフォーク・ソングは始まったのだが……。
スタインベックの『怒りの葡萄』のモデルになったオクラホマの砂あらし避難民たちの中から、大声で歌いはじめたのがウディだった。ギターを背負い、列車の無賃乗車で国中を放浪し、不況の中で落ち込んでいる人々をはげまし、笑わせ、組合の必要性を説いた。
国会図書館の仕事をしていたアラン・ロマックスに発見され、「アメリカのホメロス」「現代アメリカの吟遊詩人」と称えられた。その後の彼は、まさに超人的で、1958年にハンチングトン氏舞踏病にかかって病床に臥すまで、アメリカ大陸の西から東まではおろか、ヨーロッパ、イギリス、アラブ諸国まで旅をしている。ファシズム下のイタリアに出かけ、抗議の歌を歌ったことも知られている。闘病生活10年の後、1967年55歳で亡くなった。
彼はいつも「見たものしか書けない」と言っていた。そしてその言葉を生きた。これは、ウソをつかないとか、リアリズムであるとか、体験主義だとか、そんなレベルで聞いてはいけない言葉である。
「見たものしか書けない」
彼はデカルトと同じことを言ったのだ。
ウディ・ガスリーにとって歌とは、見ることの宣言だった。自分を見ること、世界を見ること。彼の歌は、彼が何を歌っているかを自分ではっきり知っている、という意味でモダンなのだった。
アーロはウディの息子だ。けれど父親が歌っているのを見たことがない。物心がついた時には父親は病院のベッドの上の人だった。父親は、まともに喋れもしなかった。元気だったころ、ウディは子どものための歌を数多く作った。こんな文章を書いている。
「子どもたちは、蟻が干し草の種を運び終えるまでもの長い時間、わいわい騒いでいる。わたしは、大声で叫ぶ子どもが好きだ。そんな子は、肺活量が大きくなり、大きくなったらワシントンの議事堂へ出かけて行き、大きな声をはり上げて、そのあまりの声の大きさと激しさに気押されて、5つか6つの法律は通過してしまうだろう。でまた、子どもたちの叫び声をあげさせてくれる」
アーロとウディのことを思う時、ぼくはいつも、それが父親と息子の最良の形のように思えてくる。『放浪者の子守歌』というレコードを聞くと、アーロがどんなふうに父親を尊敬しているかが、わかる。子どもが父親を考えるとしたら、たとえばこういう形ででしかないだろうし、父親が残すとしたら、たとえばこんな歌だろう。その歌を彼の子どもたちが、自分なりのやり方で、こんなにも素敵に歌うことができる。このアルバムに参加している音楽家の多くは、その後のアメリカの音楽の土台や柱になっていく。子どもたちは何と大きな声になったことだろう。
少し前にアーロは胸をはって次のような質問を、歌で、ぼくらに投げかけた。この歌は同時期のボブ・ディランの歌と呼応している。はたして、ぼくらは胸をはって答えられるだろうか。
世界中いたるところで悩みの種は尽きない。ぼくにはそう思える。だれも何をするべきか知らない。どこにいるべきかもわからない。だけどひとつの問いかけが今も突きつけられていて、ぼくらは答えないわけにはいかない。ぼくらが今いるところから延びて行く2本の道。きみはどっちの方を行くんだい?
疲れた人たちと共に、モーゼは荒れ野を横断した。40年ものあいだ、彼らは熱く焼けた砂の上をさまよい続けたのだ。そして、モーゼはひとりになって祈った。くたびれ果てた流浪の人。その時、稲妻が岩にこれらの言葉を刻み込んだ。きみはどっちの側なのかと。
イエスはゴルゴダの丘への道をよろめきながら行った。泥棒たちと一緒に、くぎを打ちつけられ高く掲げられた。彼らが晒しものにされて死んでいく時、一人があの世には何があるのかと尋ねた。主は言った。それはきみ次第なのだ、きみはどっちの側なのかだ。
取るに足りないことのために働く人もいれば、もっと大きなことのために働く人もいる。どんなことのためにも働く人もいれば、まったく働かない人もいる。で、ぼくは神の御子のために歌うことに満足している。そして、ぼくがぼく自信に問いかけていることをきみにも尋ねよう。きみはどっちの側についているんだい?
(『WHICH SIDE』アーロ・ガスリー)
[LP ワーナーブラザーズ●P-8237R CD 輸入盤 Rising Son●RSR-CD2060]
ぼくはロックンロールと同い年である。ロックンロールがいつ生まれたかについては諸説あるのだが、結局1955年に落ちつくんだろうと思う。この年、映画『暴力教室』のテーマに使われたビル・ヘイリーの『ロック・アラウンド・ザ・クロック』がティーンエイジャーの間で大ヒットし、プレスリーが爆発的な人気を獲得し、チャック・ベリーが初シングル『メイベリーン』をヒットさせ、リトル・リチャードは『トゥッティ・フルッティ』を発表。そして12月、カール・パーキンスは自作の『ブルー・スウェード・シューズ』を録音した。黒人のR&Bと白人のカントリー音楽が時代のまん中で合流し、真にオリジナルなアメリカ音楽が濁流のように誕生したのだった。
しかしロックンロールは、その熱いエネルギーを疎まれ、白人を黒人化する、若者を堕落させると嫌われ、体制の圧力に屈服するような形で、ほんの3〜4年ほどで終わってしまう。その後に、いわゆるティーン・アイドルの時代が来る。けれどロックが終わったことに気がついた人は少なかったという。われわれは一般に50年代後半から60年代前半のアメリカの流行音楽をひとまとめにオールディーズと呼んで、本物のロックンロールと、ロックンロールのふりをしたポップスの区別をできないでいる。当時のわが国の音楽雑誌を読み返してみて驚いたのだが、たとえば、白人カバー歌手パット・ブーンとプレスリーが同列で扱われている。ロックはウエスタンの新種以上のものとは理解されてなかったように見える。そして、あっという間に「プレスリーはもう古い、これからはリッキー・ネルソンだ」というような発言が目立ってくる。もうロックンロールと関係のないおしゃべりが始まっている。
ロックンロールの初期のエネルギーを、レコードだけから聞き取るのは、すごく難しいことだ。ぼくらは様々なマス・メディアによる過剰な刺激で感覚をマヒさせられているから、プレスリーやチャック・ベリーのオリジナルを聞いても、なんか間のびしてるなと思ったり、チューニングの狂いばかり気になってしまったりする。この難しさというのは、過去の作品と出くわすとき、音楽であれ絵であれ、文学であれ、いつもつきまとうものかもしれない。しかしロックの場合、それがずっと切れ間のない現役のメディアであるかのように、なんとなく思わされているから、よけいに、こちらの目が曇ってしまうのだ。ぼくらは昔のロックを聞いて、ああ、やっぱりロックも進化してきたんだなと思う。今の方が技術も進歩しているし、いいに決まってる……だが、それは大マチガイだ!
「今、ロックと呼んでいる音楽は本当にロックなのだろうか?」というクエスチョン・マークを、ぼくらはあらかじめ奪われている。
「俺達は悪魔を振り払ったんだぜ!」
とカール・パーキンスが言ったことがある。彼は謙虚に、自分のスタイルは黒人のブルースをスピード・アップしたものにすぎないと告白する。
「ブルーグラスと黒人のブルースにドラムビートがつけば、それこそロカビリーのすべてだよ。まさに、そのものだ」
しかし、ロックがブルースと決定的に違うのは、悪魔を振り払ったことだと言うのだ。
「悪魔の感情を振り落としもしないで、どうやって人々をハッピーにしたり、立ち上がってダンスを踊らせたり、体を動かしたり、楽しませたりできるんだ? 俺は「ボッピン・ザ・ブルース」って曲を書いた。俺たちがやったのは、まさにそれなんだ。ロックがもともとブルースだったってことも忘れちまったのさ。なにしろ、ブルースをぶちのめしちまったんだから! そいつはアップ・テンポで、リズムそのものだった。車の支払いや、たまった家賃の心配なんかする奴は、だれもいなかった。だれもが音楽に合わせて体を揺すって、安酒場の床に埃を振り落としていたのさ」
そのロックが逆に「悪魔の音楽」と決めつけられ、巧妙に砂糖菓子音楽にすり替えられていく。パーキンスは交通事故で重症を負い、結局復帰しそこね、アル中で自滅する。多くのロッカーが一度に死んだり、挫折した。息の根を止められたかに見えたロックンロールの耳に、遠くから力強いビートが聞こえてくる。イギリスの港町で、貧乏人の息子たちが古ぼけたレコードを集め、ギターを手にし、レコードをマネして歌い始める。ビートルズのレパートリーの中でパーキンスの歌が再び悪魔に挑戦状をたたきつける。それがどういうことだったのか、やはり、ぼくらには見えにくい。ビートルズの音楽ですら、すごい早さで砂糖にまみれていくのだ。
『ブルー・スウェード・シューズ』にはプレスリーをはじめ、多くのカバー・ヴァージョンがあるが、作者自演の持つ一種の「のどかさ」を再現できたものは少ない。
なんだか、力んで、つんのめりがちなぼくらの前に、カールはすっと立ち、軽くジャンプする。このオジサンは、ただ「俺の青い靴を踏むなよな」って歌うだけだ。その歌が世界中の青春をジャンプさせてきたのだ。
時間をかけ、立ち直り、息を吹き返したカール・パーキンスは、今日もどこかで大事な青い靴のことを、カッコよく歌っている。
【CD テイチク●20DN-83 輸入盤 RHINO●RNCD-75890】
道の真ん中に
ジョン・リー・フッカー [ アローン ]
 チャック・ベリーが、こんなことを言っていた。
チャック・ベリーが、こんなことを言っていた。
「ブルースの詞なんて、あっという間にできちまうぜ。『ベイビー、行かないでくれ。ベイビー、行かないで。こんなにおまえを愛してるんだ。ベイビー、お願いだ、行かないでくれ』こんなもんでいいだろ? 俺はみんなが聞きたいと思うものなら、どんな詞だって書いてみせるぜ」
たしかに、そうかもしれない。ブルースは、だれにでも、すぐにできてしまう。ブルースを書くのに、その人が黒人である必要はない。ブルースはどこにでもころがっている。時々ぼくは、どんより先が見えない水面下を、藻をかきわけながら泳いでいるような気分になる。いつになったら、顔を出し息を継げるのだろう。そんな時、ブルースの中にいるのだ。いや、考えてみると、これまでの人生のほとんど全部がブルースの中だったかもしれない。ブルースは呻き、叫び、吐き出し、泣き言をいい、突き放そうとし、振りほどこうとし、笑い、時に茶化し、歌い、踊る。
十何年か前、東京にでてきたとたん、ぼくはブルースにとりつかれた。レコード屋で、何気なく手にしたフレッド・マクダウェルのLPを、うっかり買ってしまったのが始まりだった。レコード・プレーヤーを持ってなかったから、女の子の下宿で聞かせてもらった。いや、そんな言い訳をして、上がり込んでしまったんだった。針を溝に落とし、ふたりでドキドキしながら聞いた。その子もブルースにとりつかれていった。
ギターを友だちから安く買って、朝から晩までブルー・コードばっかり弾いていた。その小さなギターは、すぐに、もっと上等なギターが欲しくなったんで、女の子に売った。女の子もブルースを弾けるようになった。
ブルース・ハープ(ハーモニカ)のうまいやつがいて、いつもジミー・ロジャースの『ウォーキン・バイ・マイセルフ』を心の中で口ずさみながら、シャッフル・ビートで歩くのだった。そいつはブルースをもっと太い声で歌いたいからって、毎朝起きぬけに枕に向かって大声でがなりたてて喉を鍛えていた。たしかに声がだんだんブルースらしくなってきたけど、あれは枕のおかげじゃなくて、シーツの上での出来事が、あいつの中に溜まっていったせいだったかもしれない。ぼくらは、男と女のことばっかり考えていた。
ぼくは大学をやめて、会社勤めをしていた。わずかな給料は全部ブルースのレコードに化けた。メシは例の女の子にたかっていた。レコード・ラックがわりの安物のカラー・ボックスが、3個4個と増えていった。ふたりは反対に痩せていった。女の子とぼくの、水面下の日々の、大事な大事な、にがいにがい思い出と、重い重いレコードの荷物は、引越のたびにぼくに悲鳴をあげさせる。
女の子とぼくは結婚した。どこにでもブルースの大荷物を連れて住んだ。何回理不尽に、のら猫のように追い出され、何回イヤなやつらに頭をペコペコ下げて、住みかにありついてきたことか。
知らない間にブルースを聞かなくなっていた。それは決してぼくらが豊かになったせいでも、忙しくなったからでもない。
「思い切って、捨てよう。一枚だけ残して、捨てよう、いや、売ろう」
こないだのこと、ぼくは女房に提案した。
「いいよ、賛成」
と、彼女。「何残す?」
「うん、ジョン・リーだな、やっぱり」
ジョン・リー・フッカーの『アローン』っていうアルバム。最初、ハーモニカ吹いてたあの野郎が貸してくれたとき、擦り減って、パラフィン紙を口に当てて歌ってるみたいなジョン・リーの悪魔の声が、せつなかった。せつないのに元気が出てくる、不思議な音楽だった。道の真ん中に一人っきりで立っている音楽だった。こんなに強烈で魅力的なのに、彼には亜流がひとりも出ていない。ロバート・ジョンソンのコピーするのなんて、掃いて捨てるほどいるのに。ジョン・リーのブルースをだれもマネできないのは、だれもジョン・リーの人生を生きられないのと、たぶん同じ理由だ。ちょっと触ってみようとさえ思いつかないほど、そのブルースは熱い。熱いのに冷たい。いつのまにか、ぼくの心臓はジョン・リーのブギーなリズムを打つようになっていた。
『はせがわくんきらいや』からずっと、ぼくは自分の作品をブルースを聞きながら、ブルースを思い浮かべながら、描いた。長谷川君を好きなのに、「きらいや」としか言えない、それがぼくらのブルースだった。いつでも、なりたい姿と、実際との間に、裏腹なすきま風が吹いている。逃げられないとあきらめていた。ブルースの水の中は、ある意味で居心地がいい。うっかりしてると、体温でぬくもって、そこはお風呂みたいだ。長くいちゃダメになってしまう。
ここから抜け出して、はっきり言おう。長谷川君、ごめん、本当は愛してるんだ。言わないで終っちゃったとしたら、ぼくは長谷川君をきらいなままだ。
『音楽未満』マガジンハウス(絶版)より
【Pヴァイン●PCD-1854/5】
 チャック・ベリーが、こんなことを言っていた。
チャック・ベリーが、こんなことを言っていた。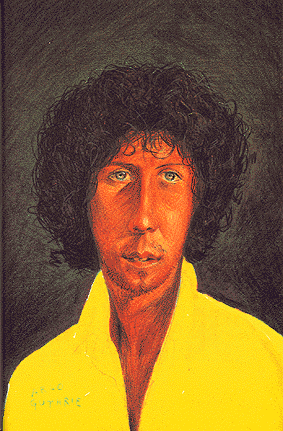 息子 アーロ・ガスリー[放浪者の子守歌]
息子 アーロ・ガスリー[放浪者の子守歌]